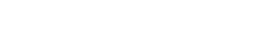永瀬一哉(インドシナ難民の明日を考える会代表)
本稿は、本会初のカンボジア公募ツアー<2001年8月>終了後に記したものである
古いパスポートでちゃんと確かめれば良いだけのことなのだが、カンボジアを訪問した回数が曖昧になっている。今夏(2001年8月)の訪問は多分14回目だろうと思う。この「多分14回目」のカンボジア訪問は私には記念碑的なものであった。
14回…。改めて計算してみる。大体、1回の訪問で最低でも20万円は使う。ということは、恐らく300万円は下らない。行かずに、このお金を直接カンボジアに寄付すれば良かったのかも…。いやいや、それはない。行って、見て、感じて、考えてこそ、支援の内容が決まる。
1989年9月、神奈川県立相模原高校に勤務していた私は、社会科の教材研究が発展し、同高生と一緒に、市内のインドシナ難民に日本語教授などのボランティア活動を行うことになった。それがすべての始まりだった。その試みは「CICR」という名称に凝縮された。
以来、CICRとして、多くの出会いを持った。難民、日本人ボランティア・支援者、国内外の難民支援関係機関の従事者、本国の人々…。こうした交流を通して、多少は活動に広がりを持てたのではないかと思う。
人と出会うことはどんなに楽しいことか。人との出会いで自分の世界が広がり、かつ、相手の世界を広げる。人との出会いに感謝し、感謝される。人との出会いが衝突を呼び、自分を見つめ直し、人間なるものを再考する。人との出会いで自分の人生が変わり、相手の人生も変わる。これこそ人生の妙味かもしれないと思うようになった。
CICR活動には本当に多くの方々のご協力を頂いている。一度もお会いしたことはないが、ずっと支援を続けて下さっている方もおられる。お一人おひとりのお顔やお名前を思い浮かべつつ書き連ねていくと際限がない。本当にありがたい。これらの方々の後押しを得て、カンボジアに独自の世界が形成されていった。「CICRの世界」と言えよう。
このCICRの世界を通して、私はカンボジア訪問の度に色々なことを学んでいる。余りにも対比的な日本とカンボジアの状況に思考はめぐる。
豊かさや利便性の追求だけでよいのだろうか。カンボジアは確かに資本主義的観点からすれば、最貧国と呼ばれてもやむを得まい。だが、その尺度だけで判断するのは何かが違う。といって、彼らが貧困から脱出したいと願うのも当然のことだろう。
どのような社会のあり方が一人ひとりの有限の人生をより充実させるのか。カンボジアの中でも、さらにひっそりと生きている地方の村の子ども達には、今、どんな教育が求められているのか。ゴミ処理場で暮らす最貧層の人々には、今、何が必要なのか。根本的な社会構造の改変に期待する一方で、それを待っていては、今、そこにいる個々の人生は終わってしまう。
トンレサップの湖面に浮かぶ水上生活者たちの船の家屋。その横をすり抜ける行きずりの私のモーターボート。インドシナ半島の巨大な湖で、日々、最期の日まで、彼らは魚を捕り続けるのか。人生とは一体なんだ。
書物の知識だけで議論することは観念的なものに過ぎないとカンボジアで悟った。肌で感じ、悩み、ジレンマに陥った時、その思考を整理、発展させる補佐役が書物だと、私は確信するようになった。
Experience without learning is better than learning without experience〔学問なき経験は経験なき学問に勝る〕
私はこの言葉に共感する。経験は何ものにも変えがたい財産だと思う。
カンボジアと日本のものの考え方の違いには歴然たるものがある。日本人として違和感や不快感を覚えることはしばしばである。こうした感覚に陥った時、あくまでも日本の文化を背負っている自己を思い知らされる。
同じインドシナでも、隣国のベトナム人の行動様式は日本人には良く分かる。日本人とベトナム人は大枠では同じような土俵で思考しているように思われる。それに対して、カンボジア人は違う。カンボジア人とベトナム人の相互の感情は決して良好ではないようだが、政治的関係を脇においても、それはむべなるかなと思う。
帰国後、「カンボジアにはうんざりした。もう、しばらく行かないよ」と言いつつ、1ヶ月もしないうちに、「今度はいつ行くかな」とカレンダーをめくり出すという私のパターンに妻は笑っている。カンボジアの何が私を引き付けるのか?
一方、在日といえども、カンボジア人はカンボジア人である。決して日本人の感覚とは同じではない。彼らに唖然とすることは少なくない。では、なぜ交流を続けるのか?
このことは真剣に考えれば考えるほど、なんだか良く分からなくなる。
飛行機がプノンペンに着くと、私は故郷に戻った思いがする。プノンペンの空港から外に出た瞬間、今までずっとカンボジアで暮らしていたような錯覚に陥る。ホーチミンシティやバンコクにも何度も行っているが、決してこうはならない。これは何なんだろう。
結局、どこかで波長があっているということなのだろうか。答えが見えるのはまだ先になりそうだ。尤も、最終的、感性的解答はともかく、少なくとも次のことは確かに言える。
CICR活動を通して、私はマイノリティーの苦悩を知った。在日外国人はマイノリティーである。いくら不自由や痛みを感じても、マジョリティーたる多くの日本人はその苦悩を知らない。マイノリティーの声はマジョリティーにはなかなか届かない。日本の社会システムの中で、カンボジア人の「痛い」と言っている声が聞こえてしまった以上、知らぬふりはできない。
カンボジアという国は国際社会でのマイノリティーだろう。人口は1000万人余。神奈川県より少し多い程度。GDPは世界最低水準。カンボジアの声はなかなか世界には届かない。超大国の国際戦略に左右される。冷戦構造の下で、カンボジアは戦乱、混乱に巻き込まれた。インフラストラクチャー(社会基盤)は破壊し尽くされた。そこに生きる人々―特に最貧層に位置づけられた人々―の生活環境は我々日本人の想像を絶するものがある。そうした現実を知ってしまった以上、知らぬふりはできない。
国策を背景にした国家レベルの支援はそれに相応しい組織・機関に期待する。私は限りある人生を背負った民衆一人ひとりと関わりたい。ささやかでも、できる範囲の支援を民衆に続けたい。
親しくしているカンボジア人から、「あなたの前世はカンボジア人だ」と言われたことがある。カンボジア人の表も裏もある程度分かりかけてきたかもしれない私を仲間だと評してくれたようで、うれしかった。
このようなCICRの世界。そうそう得がたい世界。その世界に他人様(ひとさま)をご案内し、カンボジアとのリンク役を果たしてみたいとの思いが、いつの日からか、私の中に醸成されていた。きちんとしたプランを組み、目的を明確にし、その趣旨に賛同された方々と一緒にカンボジアを旅したい。
コン・サンロート副代表と2人で慎重に何度もプランを練り直した。内容も行程もかなりハードとなった。プノンペンの現地旅行会社とはEメールで細部を詰めていった。その際、カンボジアではまだ通信手段や交通手段が必ずしも十分整っていないため、現地旅行会社には下準備のため遠方まで、大変な思いをして、直接足を運んで頂かざるを得なかった。
こうして出来上がったツアーを「CICRスタディー&ボランティアツアー/カンボジアの大地で何が見えるか」と名付けたは良いものの、海外旅行につきものの夜の息抜きすらほとんどない。そもそも訪問先がそういう所ではない。本当にこんなツアーに応募者があるのだろうか。私の一方的な思い込みではないのか。正直、不安が付きまとっていた。
だが、2001年8月9日、記念すべき日を迎えることができた。23名のツアーとなった。8月15日の帰国まで1週間、全国各地からの善意の集積―ピアニカと大量の衣類。靴。ノート・鉛筆等の文房具など―をカンボジア各地で配布しながら、ボランティアと学習を行うツアーを実施できた。ご応募頂いた方々には改めて心より御礼を申しあげます。また、スタッフの諸氏にも深謝致します。中でも南アジア史研究者の関根秋雄さんのアンコールワット解説と、通訳担当のサンロートさんの精通した日本語はこのツアーの支柱であった。
最後に、主催旅行社をお引き受け頂いた(株)風の旅行社、ツアーの広報や支援物資の呼びかけにご協力を頂いたFMさがみ、朝日新聞、神奈川新聞、タウンニュースなどのマスコミ各社、グリーンタウン高尾自治会(東京都八王子市)、そして、ツアーを陰で支えて頂いた現地関係者の皆様に御礼申し上げます。